さて、前回の記事で省令による審査基準の改正の話が流れていました。
その中で、「常勤職員1名」という要件がありましたが、「常勤」という単語がなんかふわっとしてましたよね。
なので、今回はその「常勤」についてみてみようと思います。
従来の「常勤」
いきなりですが、手元の資料にはこうあります。
ん?なんも解決してないような…。
注釈がついてるので、そこも読んでみましょう。何々…?
なるほど、定義が存在しないのか。
じゃあ、なんでこんな単語が出来てるんだ?
ということらしいです。
なので、無理やり定義を策定するなら
①就業規則等に定められた、所定労働時間と等しい労働時間が契約上結ばれている。
ことが常勤の基本的な考え方といえるのではないでしょうか。
一言で言うと、「非常勤でない=常勤」というなんかパラドックス表現ですね。
補論:パラドックス表現
非常勤でない=常勤という表現は、一般の人にはちょっと馴染まない表現だと思います。
でもこれ、法律だと時々出てきたりするんですね。
一番有名なのは、刑事訴訟法における「任意捜査」
あれ、職務質問とかで「任意」だから拒否できるという文脈で有名ですよね。
実際のところ、拒否できるかどうかはさておいて、あれは『強制ではない』という文脈で「任意」という表現が使われています。
法令上は任意捜査という単語や概念はありません。
要は、学術的というか判決文などで「強制の捜査ではない捜査」という表現をする上で、使われている表現なんですね。
他の許認可における常勤
実はこの「常勤雇用」という概念は他の許認可でも登場します。
例えば建設業の許可であれば、常勤の役員という縛りがあったり、
障害福祉施設の方では、常勤の指導員というかたちであらわれます。
まぁ、よくよく考えてもみれば、事業をするのに職員が全員非常勤というのもなんか変な話ではある訳でした。
そんなわけで、行政手続きにおいて、「常勤職員を求める」というアクション自体は、割とどこにでもある者なのですが、今回はそれがちょっと悩みの種だったりします。
常勤性の維持
引き続き、他の許認可でのお話しですが、
許認可において常勤が求められる場合は、常勤者がいなくなった瞬間に原則許可がなくなります。
なので、実質的に1人常勤の状況って結構危ういんですよ。
許認可の種類によっては、元々1名しか配置を要しないものは、暫定的な以降とかみなしとかあったりしますが、基本的には1名だけ常勤ってのは許認可の体制上あんまりよろしくはないです。
なので、今回の在留資格の基準において、常勤1名をどう解釈するんだろうかとも思ったりしてます。
在留資格における常勤の考え
個人的にあたまを悩ませているのが、この「常勤」を維持する必要はあるんだろうかということです。
その他の在留資格でも常勤を求められることはありますが、それはあくまで在留する外国人本人の話しであって、解雇されたなら再就職に向けた特例期間だのなんだのって話にスライドするのですが。
今回の場合は、外国人の方が雇用をしないといけないという建付けなんですよね。
じゃあ、雇用者がカッとんだら、在留資格どうなんねん?というのが僕の悩みどころです。
トンデモ在留期間までは維持できるよ。というのが、他の在留資格とのバランス上十分にあり得ますが、それだと
申請時に雇用しておいて、即切ったらよくない?
いや、士業としてその手を薦めるわけはないのですが、この手の裏道みたいな話は絶対コミュニティで広がるよなぁと。
で、一関与者としては、そういったムーブを取られると、こっちがそうゆう指導をしたんじゃないかとか、そもそもの申請書類に疑義があったんじゃないかとか、痛くない腹を探られる道になっちゃうんですよね。
そんなわけで、この辺はパブリックコメントでの意見応募行きかなぁと思ったりしてます。
終わりに~日々調査~
以前にもお断りしましたが、本記事は令和7年の9月時点です。
行政体としても意見公募の段階なので、確定的な話はこれといってない。
とはいえ、懸念点みたいなものは書き出しておいて、みなさまが考えるきっかけみたいなものになってくれたら、僕としてもありがたいので、ここに書き残しておきます。
それでは、また。
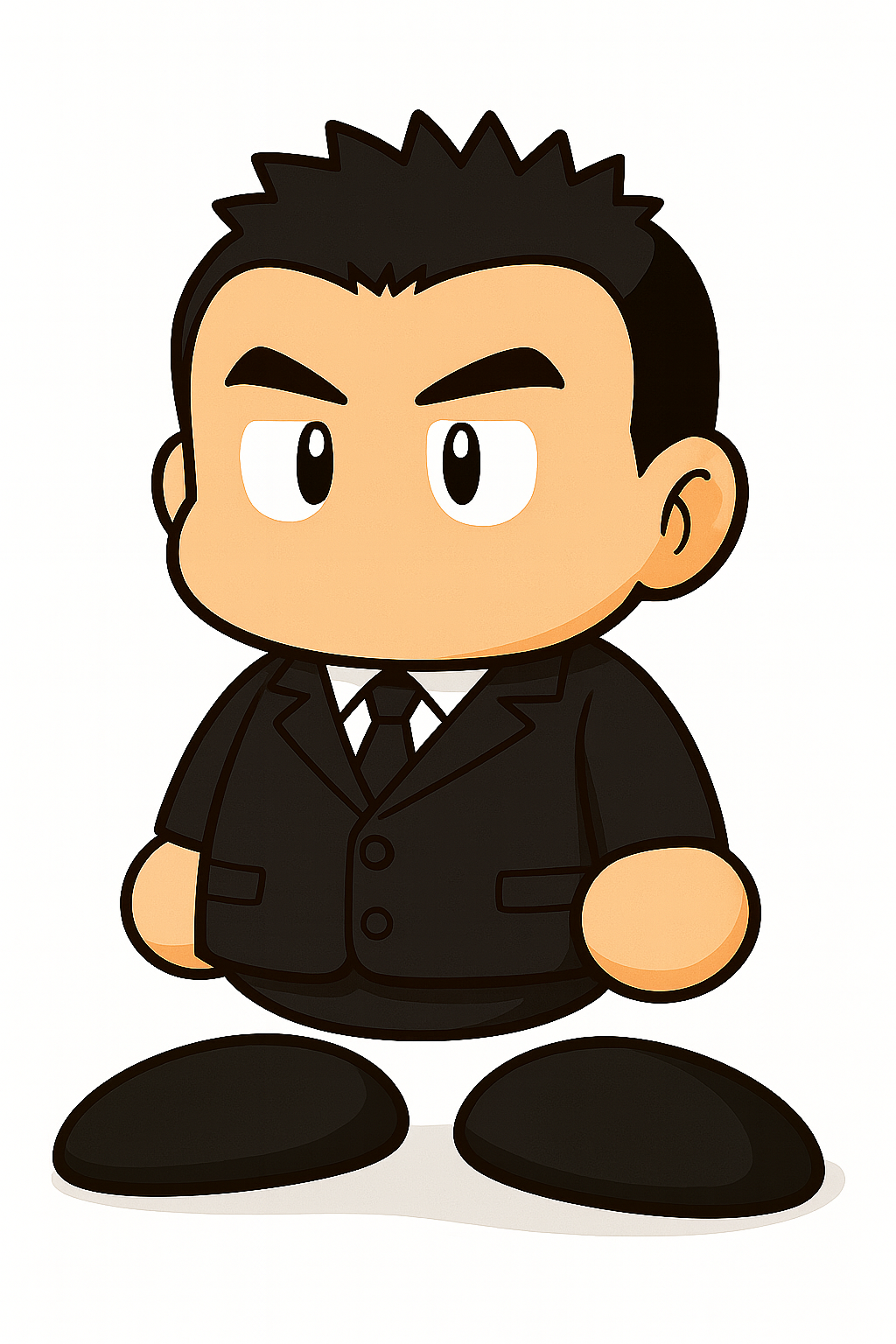


コメント