今回はちょっと雑談。
別に知っててもいいけど、知らなくてもいいシリーズ。
テーマは押印の廃止制度についてです。
とりあえず、何かしらの制度が廃止されてるので、手続き的には一つ楽になった…と思いきや、そうでもないというのが、今回のお話しだったりします。
押印廃止とは
おそらく皆さん、どっかで聞いたことがある話だと思います。
令和2年ごろ、ちょうどコロナ禍の真っただ中で、行政手続きの在り方が大いに見直されるタイミングがやってきました。
というのも、コロナ禍では原則はステイホーム。
表に出るなが原則でしたから、従来の『態々行政庁に赴いて申請手続きをする』という流れも見直すことに。
その中で、注目されたのが、電子申請(デジタル申請)
実際コロナに関係する給付金などは原則電子申請という形でした。
ところで、行政手続きに要する書類の大部分に関しては、『押印が必須』でした。
しかし、電子申請となると、押印を求めるタイミングが難しい。
作った書類を印刷して、押印して、スキャンして送信?流石に手間がかかり過ぎる。
なので、電子申請で作られた行政書類が、本人のものであるという証明を押印なしで認める必要が生じたため、押印が不要であるという流れを作らざるを得なかったように思います。
まぁ、オチとしては現場は混乱することがそれなりにある。というのが正直なところです。
次から、押印に関して困っているケースをお話ししましょう
委任状の押印
僕たちの業務ではよく使う「委任状」
誰誰が誰誰に、どんな権限を渡したのかを明示する書類ですね。
これ、実は現場において『押印不要になっていない書類』だったりします。
押印廃止はあくまで『行政書類に関して』の話なので、委任状は民間の関係性を証明する書類にあたるため、それには押印を貰ってきてくれと。
せっかく行政書類に印鑑がいらなくなったのに…結局こっちには押すんかい!という。
しかも、一律して押印必要であればわかりやすいんですが…委任状にも押印が不要という行政もあったりします。
その場合、署名を求められることになるのがほとんどです。印字で記名はダメと。
それはそれで、レビューが増えて面倒な。
なので、うちの事務所の対応としては、とにかく委任状には押印を貰うということで、統一しています。
行政による対応の異なり
↑の委任状で「あっ」と思われた方もいるかもしれませんが、そもそも押印廃止は義務ではないのです。
基礎的な行政法のお話しですが、日本の行政組織として、国と地方自治体は並列の関係であり上下の関係ではありません。
税収やそれにまつわる交付金の関係上、上下関係に見えることが多々ありますが、法令上は地方自治体は地方自治権として国とはまた別個の統治能力があります。
もっとも、地方自治体も独立国家というわけではないので、国の政策の方向に足並みはそろえていくのが基本です。
なので、国が押印廃止!と決めても、基本は揃えますが、現実的に地方自治体が独自に行っている行政手続きがすべてそれに追従するのか?そもそも追従できるのか??というとまた別の話になるわけです。
なので、手続きによっては押印が不要を徹底している自治体もあれば、まだまだその流れに追いつかない又は、(電子申請に限るなど)限定的な対応をする自治体はあるにはあると思われます。
なので、やはり原則的には押印はもらっておいて損がないという、なんだかなという状況が結構あったりします。
職印について
これは僕たち行政書士特有のお悩みです。一般の方は特に問題がない話。
実は、僕たち行政書士が作成した書類には、『職印』を押す必要があります。
落款みたいなもんです。
しかしこれ、きっちり行政書士法で定まっているという。
なので、僕も持っていますし、書類を作ったら必ず押します。
ところが、押印不要の流れから、申請書類に押印の欄が結構な確率で消えてます。
なので、いつもどこに押すべきが、結構迷う。
そもそも、行政庁が押印要らんって言ってきてるのに、態々自分の名前の横に押すの、ちょっと不安だったりします。これのせいで、なんかいわれたりせんかなってw
最後に…押印の意味
最後に、ちょっとだけ。そもそも論です。
皆さんは何故「押印があれば、本人が承諾した書類である」と認めるのでしょうか。
モノ心着くころには、郵便屋さんに印鑑を押すことが広まってると思うので、割と社会的に自然と身に付く常識だったりします。
ところが、実は法律上定めがきっちりあったりするんですよね。この印鑑による意志の証明。
気になった方は、民事訴訟法の228条4項と二段の推定をググってみてください。
押印は廃止…といっても、この条文がある限り、押印の意味が変わることは無いですし、意味がある以上はやって備えて損がないというのが正直な感想でした。
それでは、また。
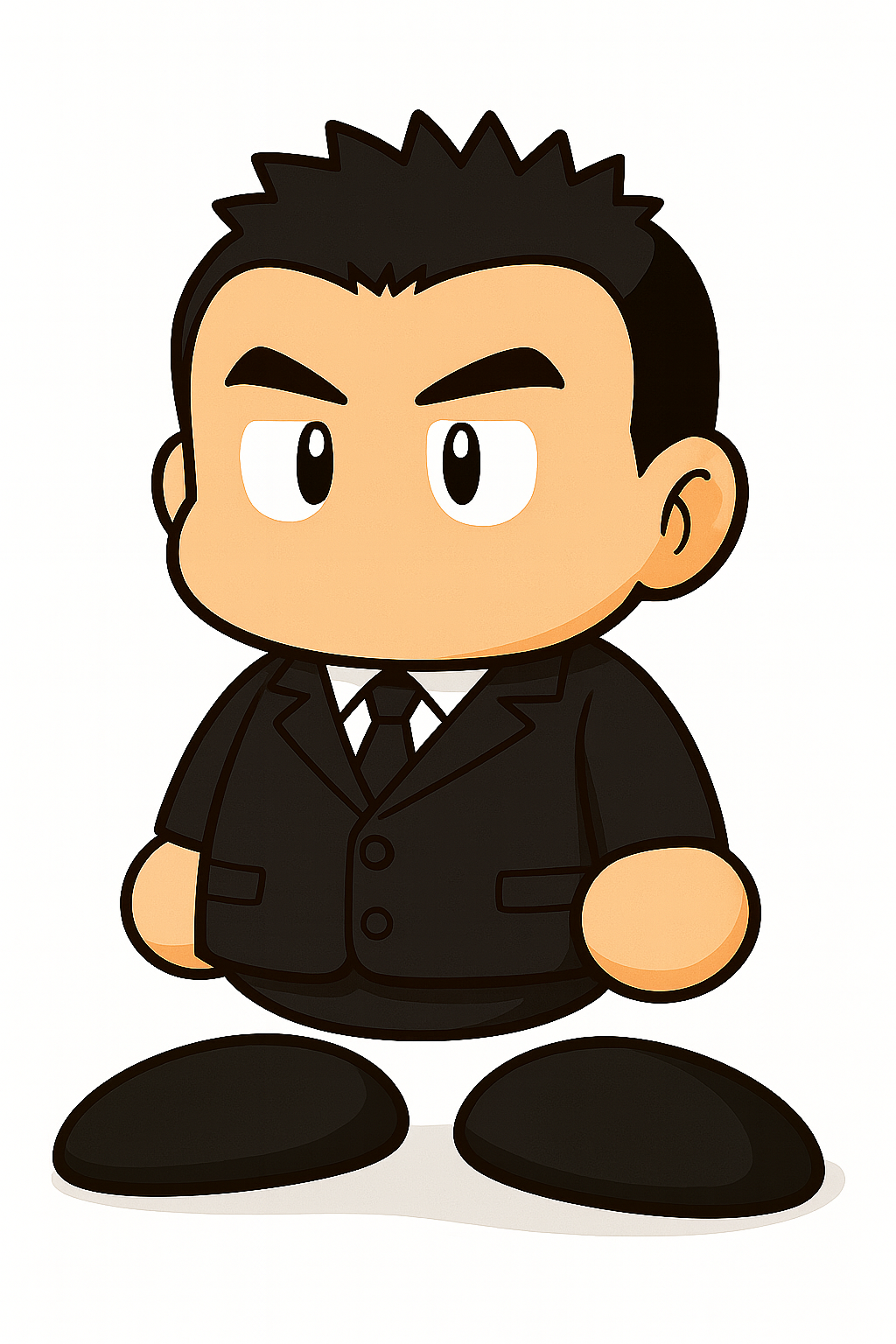


コメント