はじまり
ある一幕。
「実は、うちの会社の〇〇が退職代行を使って辞めましてん。急におらんくなって、出社する意思もないし、代行会社が相手で埒があかんから、翌日付けで退職ということになりまして。」
最近はやりの≪退職代行サービス≫
色々と世相を反映しているというか、それ自体が弁護士法との関係でどうやねんとは思ってますが、今回の問題はそこではありません。
「ちょっと待ってください、確か〇〇さんって、許可とってる事業の重要職でしたよね。代わりの対応はどうされるんですか」
「代わりは~」
そんなわけで、今流行?の退職代行サービスが、僕たち行政書士のメイン分野である許認可関係について、ちょっと将来的にやばい影響を与えてくるんじゃないかと思い、記事にしました。
整理:許認可制度と人的要件
行政上の許認可を取得する場合、【人的要件】が要求される場合があります。
建設業では経営管理者や専任技術者であったり、運送業では運行管理者であったり、販売業系列では販売管理の責任者が必要だったりします。
難しい言い方をしてますが、簡単に言えば、『事業を安定させる監督責任者として、経験や資格を有する人を用意しなさい。』という意味です。
当然ながら、相応に厳しい経験年数や資格を要求されますので、おいそれとは用意できません。
ほかの要件は足りてるんだけど、経験の年数が足りなくて人的要件を満たせないから許可をあきらめるということは、よく聞く話です。
さらに、この手の【人的要件】は許可取得時のみならず、許可取得後も引き続き充足をさせる必要があります。
退職などで交代が生じた場合は、速やかに届け出る必要がある場合がほとんどですし、交代が用意できない場合は、許可を取り下げる必要があります。
また、この届出を怠ると、それはそれで処分(ペナルティ)対象になってしまいます。
なので、【人的要件】に掛かっている人の動向は常に細心の注意が必要ということになります。
整理:民法上の雇用規定
ここからは、【辞めること】についてのお話しです。
雇止め…端的にはクビの効果発生は宣告から30日の猶予が必要であるというのは割と有名な話かもしれません。
これは、労働法上のルールです。
では、『雇われている方が辞めるといった場合の日にち』のルールは何処にあるのでしょうか。
実は民法にこんなルールがあります。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
なので、被用者が
即日辞めたい
と申してきても、使用者としては
2週間後な
と言える余地が残ります。
但し、この規定はあくまで目安です。
重要な点ですが、この規定は当事者同士が話し合いで合意に至らなかった場合のルールであって、当事者が合意していれば、法定よりも短い期間で退職とすることができます。
(講学上、任意規定と言います)
なので、例えば即日辞めたいという意思表示に、合意をしてしまった場合は、即日退職という処理になります。
アドバンス:一般法と特別法
アドバンスですので、読み飛ばして大丈夫です。
ここを読まれて「ん?」と思われたかたもいるかもしれません。
さっきクビは30日とあったのに、こっちは『各当事者が申し出てから2週間』とあります。
これは、一般法と特別法の関係というものがありまして、一般法に書いてあることが不都合な場合に、特別法を定めてそちらを優先します。
そうです、労働法の規定は特別法で、民法は一般法なので、労働法は民法より優先されます。
パワーを持っている使用者の雇止めが、雇用者の辞意と同じ期間ではバランスが悪いので、クビが30日に調整されているのですね。
他方で、労働法上は『被用者からの辞意に関する日にち規定』はありませんので、そこは民法上の規定が用意されます。
尚、民法の同条は雇用の形態によってルールを少し変えていますので、気になる方は原文を当たってください。
整理:許可がトぶ
許可がなくなったら、またとればいいじゃない。
どこかの王侯貴族みたいな言い回しになりましたが、ところがぎっちょんそんな簡単な話ではありません。
例えば、建設業者の場合、建設業許可を喪失しても、一応現在の工事を継続することはできますが、発注者に対して許可がなくなったことを2週間以内に通知しなければなりません。
このへんはシンプルに信用問題ですね。
さらに、当然ながら以後の新規受注に関しては建設業法上の制限(請負額500万円以上は受注不可)を受けます。
折角従来の元請けさんからお話が来ても、「今はダメですわ」というのはアレですよね。
また、許可の失い方によっては次回の許可取得に影響が出ます。
人的要件の喪失を正直に申し出て、許可を取り下げ、新たに人を用意して…であれば、スムーズに許可の再取得に向けて動けます。
しかし、例えば「変更の届出を忘れていた」等によって、ペナルティにより許可が取り消された場合、取消しから数年間は許可の再取得が不可能になる場合があります。
この辺は許可業種ごとに対応は異なりますが、最悪のルートとして認識はしておいてください。
問題点:人的要件者の退職代行
それでは本題です。
事業の許認可上、人的要件にあてている人…例えば、建設会社であれば、専任技術者(その事業所において、工事技術を統括管理している人。建設業許可の人的要件の一つ)が突如、退職代行を利用して辞意を申し出てきた場合です。
この場合、事業所としてはどのように対応するべきでしょうか。
対応:その場では承諾しない
究極的な結論を先に述べますと、その場では絶対に早期の退職に同意しないことが重要です。
ネガティブ要素として、退職が成立しない間は【給与】が発生する可能性がありますが、それでも、迂闊に即日退職を認めた結果、許可に悪影響がでる憂き目のリスクに比べれば些細な事です。
先の規定通り、辞意の通知を受けた段階で、例え拒否しようとも2週間後には雇用契約は解除されます。
とはいえ、2週間の時間ができるので、その間に人的要件を整理したり、必要な届出を作ったり…。
専門家に相談する際にも、相談時間が必要であれば、相談先の専門家が事実確認に走る時間もあった方がよいですし。
なんしか、ポンと抜けられると、何が不都合かわからない状況に陥るのが本当に危ない。
感情的に【もう来る気のない奴を抱えていても仕方がない】と思われると思うのですが、一応在籍しているという状況が、次の体制を作り上げるための時間を生み出してくれます。
そこをぐっと抑えていただけると、専門家としては非常に助かります。
対応:専門家に相談する
対応を取るとなれば専門家に相談しましょう。
その許認可を取得する際に利用した先生がいるのであれば、その先生が筆頭でしょうか。
許認可の制度によっては、「出勤の現実が期待できない状況」自体が危機的な状況になる場合もありえるかもしれないので、退職代行の連絡を受けたらすぐに確認しましょう。
その際に、退職代行サービスさんとのやり取りの記録があれば、なお良いかもしれません。
終わりに:まさかの時代
正直なところ、退職代行サービスの存在自体も時代だなと思いますが、それにしてもこのサービスを利用するのはせいぜい入社から3年目ぐらいまでの、辞めたくても辞めると言い出せない層がターゲットだと思ってました。
ただ、世間の流れをみていると、どうもそうではない。
なんなら中堅層だって、言い出しにくい理由があるだけで、言える術があれば辞めるのが今の時代かもしれません。
その意味では、いつ誰が辞めるか、本当にわからない状況になってしまいました。
とはいえ、疑心暗鬼のまま仕事をすることはできないのですから、せめて【この手の代行サービス】への対応については、一旦ある程度、確認しておくというのが、今の経営者に求められる知識なのかもしれませんね。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
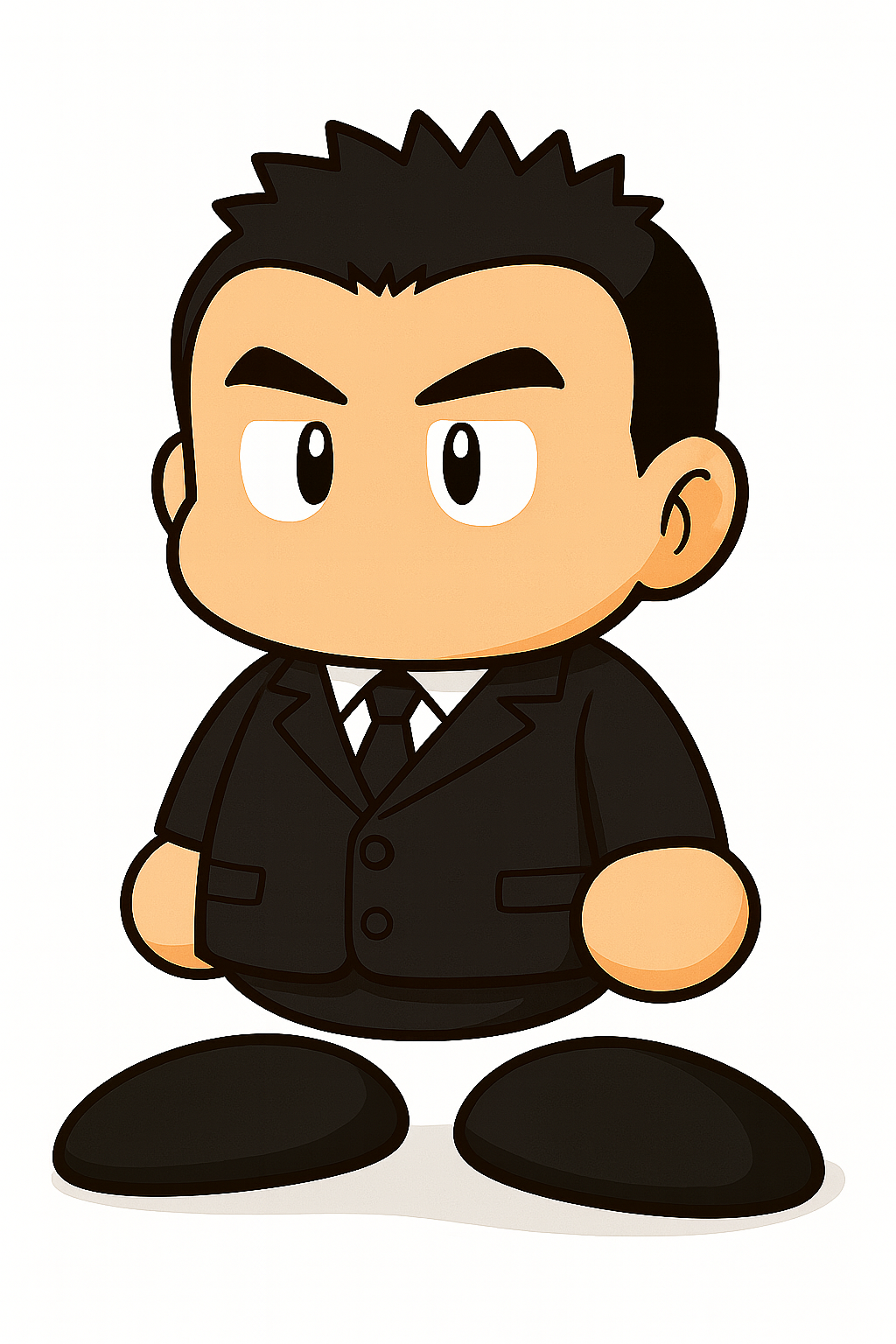


コメント