皆さん、こんにちは。
今回は少し時事的な話題です。
最近、建設業者が検挙されるというニュースを見かけることが増えています。
多くは大阪・関西万博関連の案件です。
例えばこちら
では、これは何を意味しているのか。
そして、どういう経緯でそうなってしまうのか。
今回は、そのあたりを簡潔にまとめてみたいと思います。
「許可なしで工事=違法」ではない
まずニュースの見出しを見ると、
「建設業の許可を得ずに工事をした」という文字が目に飛び込んできます。
これだけを読むと、「工事は許可がなければ一切できないのか」という印象を受けがちです。
しかし、実際にはそうではありません。
建設業法では、工事の金額に基づいて制限が設けられています。
500万円を超える工事を請け負う場合に、建設業の許可が必要になる――という仕組みです。
つまり、500万円に満たない比較的軽微な工事であれば、許可は不要です。
たとえば、
- 簡単な土木工事を行う
- 一部の部分的なリフォームや改造を行う
こういった工事は、建設業の許可がなくても行えます。
ポイント⇒500万円以上の工事では建設業の許可が必要になる。
500万円を超える工事は、なぜ許可が必要なのか
一方で、500万円を超える規模の工事となると、社会的に重要な建物や施設が増えてきます。
住宅の建築や道路の整備、上下水道の主管理などです。
こうした工事は、発注者だけでなく、完成後に利用する多くの人々にも影響します。
もし施工不良で建物が壊れれば、社会的な損害も大きくなりますからね。
だからこそ、一定規模以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可を取得することが義務となるわけです。
万博関連の建物や施設の規模を見ると、ほとんどが500万円を超えてくるでしょう。
となれば、許可を持つ業者でなければ施工できません。
建設業許可には「更新期限」がある
今回の記事の中には、「許可が切れていた」という記載もありました。
実は、建設業の許可は一度取得すれば永久というわけではなく、5年ごとの更新が必要です。
この更新は運転免許の様に即日では終わりません。
通常、都道府県知事の許可で1〜2か月程度の審査期間があります。
(ちなみに、大阪の場合は30日という基準があります)
申請をすれば良いのではなく、期限までに「許可が下りている」状態にしておく必要があるのです。
更新期限の前日に申請しても間に合わない、ということですね。
許可切れを防ぐための仕組み
許可切れを防ぐには、そもそも法令で義務付けられた仕組みを活用するのが有効です。
それが「決算変更届」です。
建設業者は、事業年度が終わるたびに自社の財務状況を都道府県庁へ届け出る必要があります。
これは、毎年行ってる(苦しい)税務署への確定申告とは別の届出です。
これを毎年きちんと提出していれば、「許可の有効期限」が近づいていることにも自然と気づけます。
会社の決算日と許可取得の日が異なるので、「おおまか」にはなるのですが、だいたい4通ほど決算変更届を出せば、そろそろ更新の時期だとわかります。
つまり、毎年届出の期限を守る意識を持つことになるので、許可切れのリスクは大幅に減らせます。
許可期限がバラバラになる理由
建設業の許可は業種ごとに取得します。
たとえば――
- 防水工事(建物に防水加工を施すなど)
- 内装工事(室内の仕上げや設備設置など)
これらは別の許可区分となり、取得時期が異なれば更新期限もずれてしまいます。
例えば、最初は防水工事の許可を取得していたが、後々経験者を雇い入れ内装工事の許可もとった場合なんかです。
この場合、それぞれの許可ごとに更新時期が進行します。
結果として、一部の許可は有効でも、別の業種の許可が切れていた…ということが起こり得ます。
発展⇒対策
対策として更新の時期を揃えることはできます。
例えば上の例で言えば、防水工事の許可更新の際に、内装工事も一緒に更新してしまい、以後更新は同時に行うようにできます。
都道府県ごとに微妙に条件が変わることがありますが、大阪の場合短くする方(今回で言えば内装許可)が6か月以上残っていれば、そろえることができます。
許可が切れていたらどうなるのか
最後に、「許可切れ」の状態が実務や安全性にどう影響するかです。
誤解のない様に先に補足しますが
許可が切れていること自体は、なんら違法でははありません。
問題は、許可が切れている状態で工事を請負い、継続したことにあります。
安全性の話
こんなことを言うとある方面から怒られるかもしれませんが。
許可が切れている業者が行った工事が直ちに建物が危険であるということではないと思います。
許可要件相当の工事体制を備えていることと、実際に許可申請をして許可を持っていることは別ですから。
究極は【体制を備えて入るけど、許可とってないだけ】という可能性があります。
先のニュースで報じられた会社の状況はこれにちかいのではないでしょうか。
なので、報道の事件の捜査は、建物自体の実質的検査に加えて、実際に対応された施工管理体制がどうだったのか(許可相当の体制だったのか)は検証されるのではないでしょうか。
ただし、これはあくまで工事の実質的な部分、建物の安全性を検証する上での話です。
法制度の話
法制度上、許可を取って行うべきとされている工事を建設業者が許可を取らずに行ったことにはかわりません。
実質的にセーフだから許す。なんてことになれば、法制度として崩壊します。
建設業許可の制度は、業界の安全性を担保する上で重要かつ初歩的な制度です。
・許可を取得している会社は、一定程度の規模・人材・経験を保有すること。
・その会社によって施工された工事の信頼性を担保します。
その信頼を侵害した業者については、しっかりとした処分が下ることでしょう。
尚、この手の処分が下った場合、該当業者はもちろん関係した役員の方々についても、新たに建設業許可の取得は難しくなります(欠格事由に該当するため)
まとめ
- 500万円超の工事には建設業許可が必須
- 許可は5年ごとに更新、審査期間は1〜2か月
- 決算変更届の提出が許可切れ防止のカギ
- 業種ごとに期限が異なるため管理が重要
- 実務的には危険性は直ちには増さないが、制度面で大きな意味がある
💡 許可制度は、安全と品質を守るための最低限のルール。
日頃から適切に管理することが、業界の信頼維持につながります。
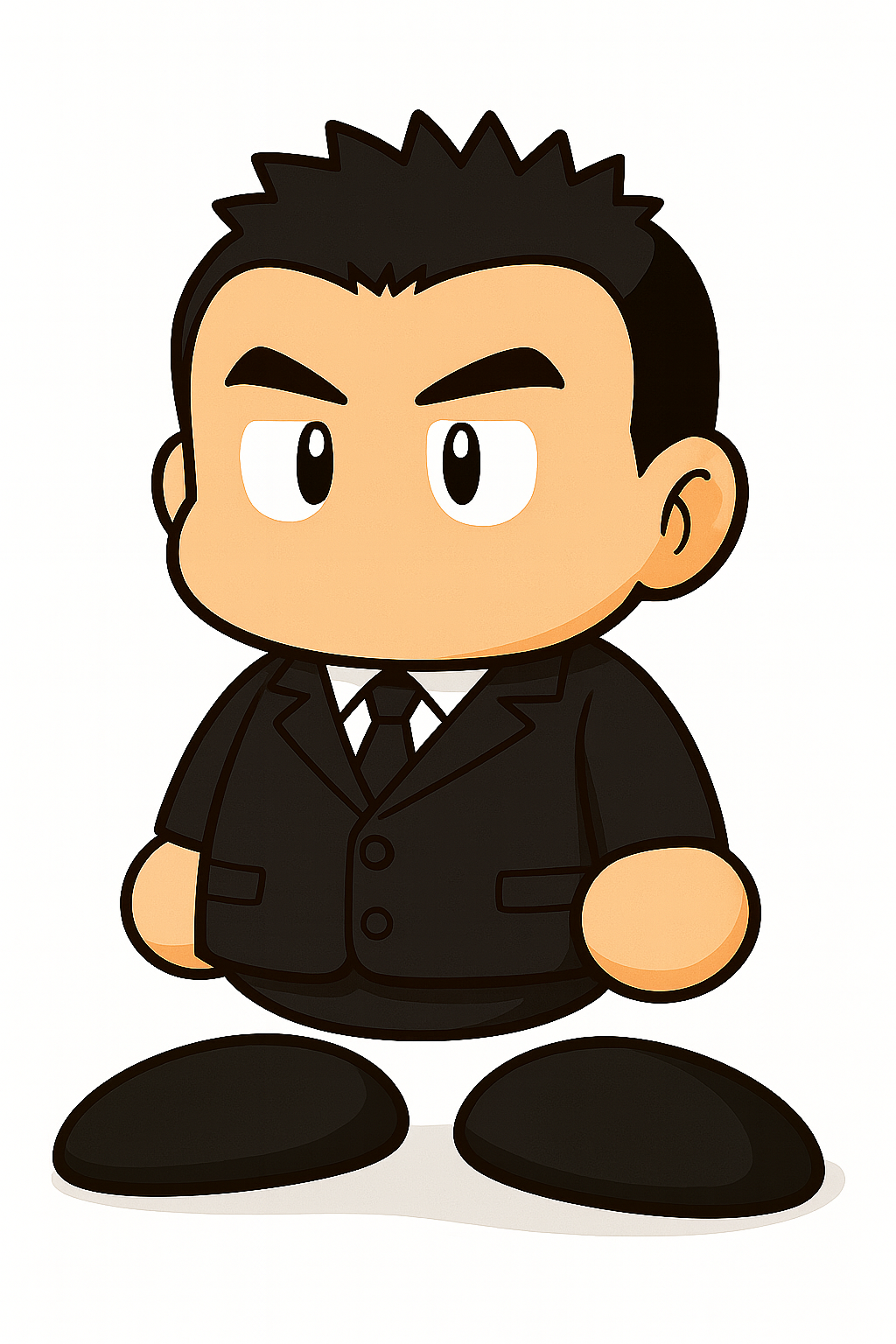


コメント