皆さんこんにちは。
今日はオープンマリッジについてです。
急な話だって?そりゃちょっとネットで話題になってますからね。
誤解のない様に申し上げておきますが、当ブログに関係者を賞賛又は批判する意思はありません。
単に突如として現れた「オープンマリッジ」という概念について、日本法的に考えてみたいという試みになります。
オープンマリッジとは
正直、僕も今回の騒動を受けて初めて聞きました。そんな単語あるんだって。
流石にわからないことは調べましょう。ちょうど今はAIという調べ物には便利なものもありますし。
オープンマリッジとは
形式上は結婚しているが、夫婦の合意に基づいて「配偶者以外との恋愛・性的関係」を認める婚姻形態のことを指します。日本語では「開かれた結婚」と訳されることもあります。欧米の一部ではライフスタイルとして議論されることが多く、ポリアモリー(複数愛)や事実婚と近い文脈で扱われる場合もあります。
なるほど?形式上は婚姻はしているけど、実質的には他人との干渉を認める形式と。
そして、この話を聞いたときに少し考えました。確か似たような話が判例であったよなと。
日本の婚姻=民法上のルール
民法上の条文はこうなってます。
ちょっと整理しておくと
ということになります。
処で、この「婚姻の意思」とは一体何でしょうか。
①形式的に同一戸籍になることを望むだけで足りるでしょうか?
それとも、②それを超えた法的効果を受け取る意思が必要でしょうか?
さらに掘れば、③法的効果を受け取るだけでなく、一定の社会的生活等関係を営むことまで求められるのでしょうか。
このように、法律の条文を読むと「文言はそれっぽくわかるんだけど、具体的にどこまで落とし込むかわからない」という状況が生じます。
このどこまで落とし込むのが妥当かを検討する作業を【法解釈】といいます。
法解釈には様々な結論があり得ますが、終局的結論は裁判所の判断、つまり【判例】によることが第一になります。
(他方で、この判例の妥当性を巡り様々な法解釈を検討する学問が法学でして、その意見が学説と呼ばれるものです)
なので、まずは判例を確認する作業が大原則です。
法解釈に迷ったら、まずは【判例】を見てみよう
裁判所「婚姻の意思とは」
昭和44年にこのような判決がありました。
ないときを、ない場合で〆ているのでちょっとわかりにくいですが、要は先の③のパターン『婚姻によって生じる法的効果を超えて、実社会上の生活等関係性を望む』ことまでを含めて『婚姻の意思』とするようです。
実際、この判断がされた昭和44年の事例ですが大雑把にはこのようになってました。
要約すると、嫡出子という身分(法的効果)を目的とした婚姻、つまり②のパターンについて、婚姻の意思を否定しました。
よって形式的な届出だけでは足りず、実社会において夫婦として活動する意思が求められることになるでしょう。
判例の適用があるかどうかについて言えば、それぞれ事案ごとの具体的な状況によって異なるところが生じますので、一概に決めつけるのはちょっと危険ではあります。しかし、裁判所が考えている『婚姻の意思』という条文文言の意味はある程度はっきりしますし、それにオープンマリッジが馴染むのか?という検討はある程度はできるでしょう。
なので、昭和44年の判例をベースにする限りは、オープンマリッジという概念の成立は少し厳しいという理解になるかと思います。
判例は法的効果に加えて、社会通念上の夫婦関係を欲する意思が『婚姻の意思』としている。
そして、判例を元にした検討として、学問のターンがやってきます。
この手の学問では裁判所の解釈を尊重する、異論がないとするものもあれば、裁判所の解釈には問題が包括されており、妥当性欠くため別の解釈をするべきだとするものもあります。
さて、婚姻の意思を巡る学説の立ち位置はというと…。
学説「法的効果を欲するだけでよくない?」
判例の言う「社会通念上の夫婦」というものは、その時代時代で評価が異なる概念です。判例が時代変異を想定した時に、将来にも妥当するようによく使うマジックワードでもあるのですが、使われた方はイマイチしっくりとこない時もあります。
特に昭和の時代の夫婦感と、令和の今の夫婦感が同じか?と言われると、すこし怪しい。
そこで判例に対して学説は、実社会的な生活関係までは必要なく、【法的効果】を欲する意思で足りるのではないか?という反論が展開されています。
他方で、【法的効果】について、一部でよいか全部必要かという点で別れもあるようです。イチブカゼンブ。
この別れは結構重要です。
法的効果の中には、推定相続人や誕生する子の身分など法定の話がありますが、同時に扶助義務や貞操義務など、(判例によって導かれた)「婚姻共同生活の基本的義務」も生じます。
所謂不倫によって慰謝料が生じるのは、この「婚姻共同生活の基本的義務」として貞操義務が法的に保護されているからです。当然法的効果が全部必要となれば、この貞操義務も守る必要が出てきますのでオープンマリッジの概念には妥当しないでしょう。
逆に一部でよいという考え方の場合、いくつかの義務については当事者同士で排除できるという考えになるのでしょうか。その場合、貞操義務を排除することの妥当性について検討することにもなりそうです。
法律「一応、一夫一妻制です」
貞操義務を排除できるかの検討ですが、一度民法の建付けを整理しておきましょう。
民法上、重婚は禁止されていて、制度としては一夫一妻を構築する家族法になっています。
この制度を前提とすると、幾らオープンマリッジの概念によって法的義務を部分的に回避できるとしても、多夫多妻による多家族を構成しかねない義務については回避はできないのではないかと思います。
所謂、公序良俗と呼ばれるものですね。
まぁ、それこそ「公序良俗こそ時代によって変わるやろガイ」と思われると思うんですが、少なくとも法定の制度を読み解いたときに、法律の社会観がそうなっている前提では、それが公序良俗というほかないです。
(なので、法改正があれば、基準が変わることもあるでしょう)
なので、貞操義務を排除する婚姻合意というものが、成立するか?というと、今の社会環境ではちょっと厳しいのではないかなというところです。
オープンマリッジがもたらす弊害
僕の考察的に、現代日本でオープンマリッジが正式に認められるかというと、ちょっと厳しいというのが正直な感想です。
では、認められなかったから何なんだ?という話しにもなるんですが、これがちょっと気分のよろしい話にならない。
ちょっとだけ見ていきましょう
婚姻が無効…で?誰が言えるの?
婚姻に限らず、日本において訴訟を提起する場合は原則として訴訟利益が必要になります。
オープンマリッジの話に準えれば、当人らの婚姻が無効とされることで利益を得る者です。
この利益を得るというのは、実質的な利益ではなくて法的利益の話です。
単に、当人らのファンの人が、「ロス」を感じたので婚姻を無効に…なんてことはできません。
この辺は訴訟法の細かい踏み込みが必要になるので、事案によるのですが…。ぱっと思いつく人で言えば、当人らの推定相続人だった人たち、要は遺産を受け取る権利があった人たちでしょうか。
婚姻が成立することで、相続の予定が大きく変わるので、この婚姻を否定したいと思う人はいるかもしれません。しかし、この【相続の予定】というものが、法的に保護に値するのか…その辺も法解釈に当たる必要があるでしょう。
この記事では完全に路線が外れるので検討はしませんが、とにかく、無効を主張できる人は限られている。ということだけは言及しておきたいと思います。
婚姻が無効だったとしても、それを主張できる人物は限られている。
当事者間に与える影響
こっちの方が胸糞気分が悪い話かもしれません。
仮にですが、オープンマリッジを誓約した当事者同士が離婚を選択する場面を仮定しましょう。一方当事者に離婚の理由を聞くと、「オープンマリッジにより排除した義務について、納得ができなくなってしまった」という場合にどのように解決に持っていけるでしょうか。
まず、ぱっと思い着いたのが、離婚を申し出られた側の対応として
請求1 本婚姻は夫婦間の義務を排することを当事者で約しているため、義務に基づく請求は成立しない
請求2 1が通らずとも、本婚姻は(義務を排除したため)昭和44年判決の言う婚姻の意思を欠き無効である。
婚姻が無効であるため、婚姻に基づく義務を基礎とした請求は成立しない。
という形で、とりあえず解消には応じるが、びた一文払う気がないという手法に出れるんですよね。
通常であれば、義務違反で慰謝料などの話になってくるはずが、肝心のその義務を排除しているため請求が難しくなるという。
離婚を求める側においては、相手方がそのような申し出、特に婚姻の無効を主張する行為は禁反言に抵触するとか、訴訟法上の技術に求めることになるんでしょうが。。。大元の昭和44年がぶっ飛んでるんですよね。一度婚姻合意したその当事者から無効主張が通っちゃってるんで…。
年齢を重ねたり、環境が変わることによって、婚姻成立当時の価値観とは変化が生じる可能性はあり得えますので、このオープンマリッジという概念、言葉選ばずに言えば、「価値観が変わった方が負け」みたいなめっちゃつらいチキンレースみたいな関係のような…?
なんか考えれば考えるほど沼というか、日本の法的感覚には合わないような気がするんですよね。。。
終わりに~図らずもサンプルケース~
僕個人的に本件の騒動の元になった某氏は認識はしていたんですが、これといって応援していたというガラでもなく。
夏祭りのあれはぶっ飛んでるなぁと思いましたが。
それはさておき、こうした変わった婚姻関係を世間もとい世界の電波の波に乗せた結果どうなるのかというのはちょっと気になるところ。
井戸端感覚で恐縮ではあるんですけどね。
それはそれとして、オープンマリッジなる独特の感性について、今の社会になじむのか?という疑問の種がもらえたのは良かったかなと。考えてみると、色々あるもんだ。
重ねてになりますが、婚姻とは究極的に当事者のお話しなんで、それをけしからんだのなんだのって、当事者を批判する気はさらさらありません。
ただ、その新しい概念の行く末みたいなものは見守ってみたいなとはおもいます。
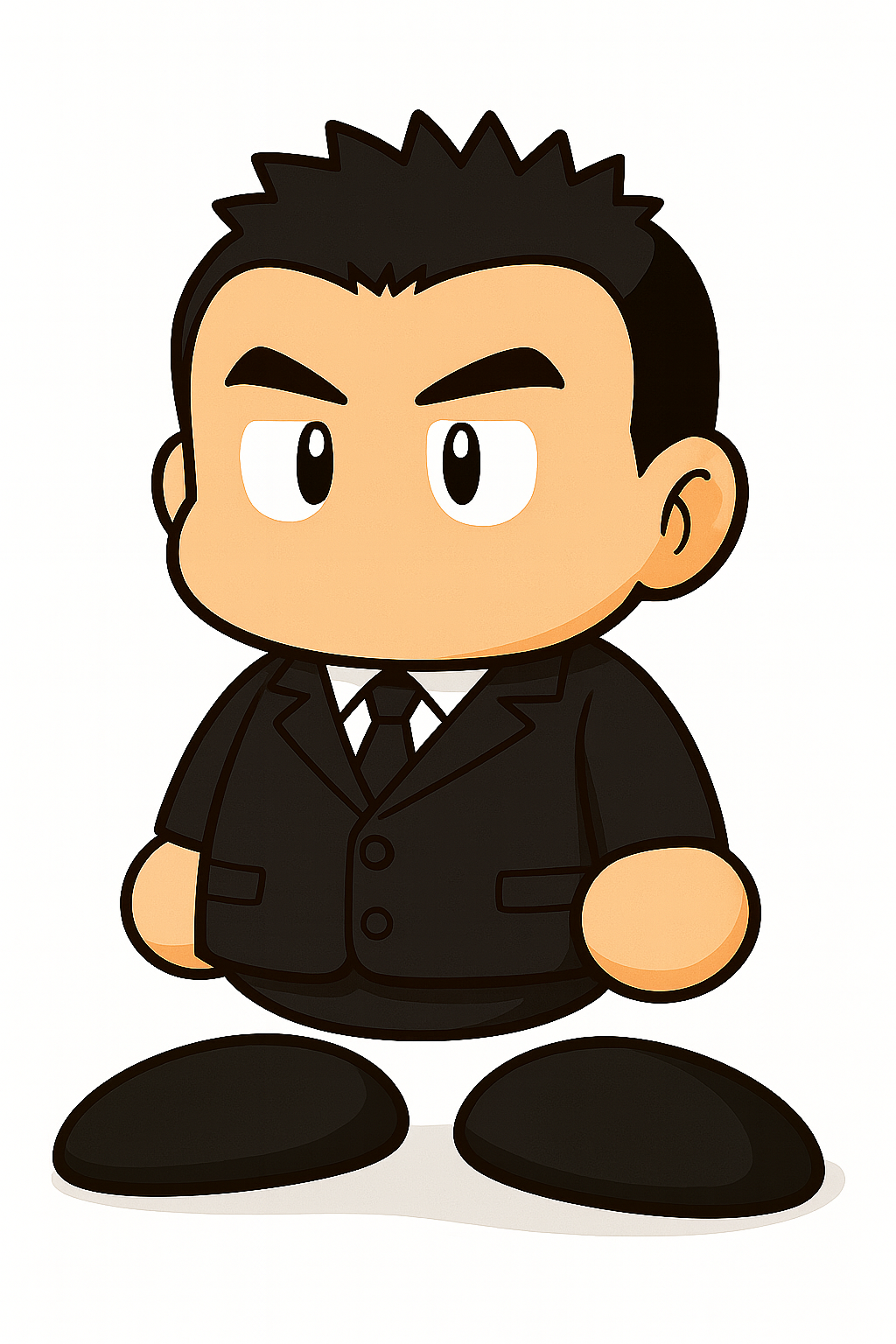


コメント