最近社会問題として、外国人との共生・・・特に地方地域での生活摩擦が問題として取り上げられるようになりました。
僕個人は純然たる日本人ですが、この摩擦に関して少しだけ思うことがあったので、記事にしようと思いました。
政治的側面というより、法的側面から見た違和感に近いものかもしれません。
それでは始めましょう。
埋葬問題について
今回、取り上げようと思ったのは埋葬に関する問題です。
ニュースでは外国人のが「土葬」にこだわるために地域住民と摩擦が起きていると報じられています。
また、行政施設としても「土葬」を行えるようにと配慮しようとしたところ反発を受けるという状況のようですね。
ところで、この埋葬という行為について、もう少し理解を進めてみる必要があるのかもしれません。
日本における埋葬と埋葬という行為
日本において、埋葬といえば火葬が一般的ではないでしょうか?僕自身も、親類縁者を見送る際には火葬が選ばれていました。日本人の感覚的には埋葬=火葬というのは結構根付いたもののように思います。
日本における埋葬=火葬
ところで、埋葬という行為は、真っ向から宗教行為であるという点は忘れてはいけません。
あんまりに火葬が根付きすぎているので、ついつい忘れそうですが、世界的に見たときに当たり前の話ではないということです。
宗教的に火葬を推奨しているものもあれば、むしろタブーとして扱う宗教もあります。これを一々指摘するつもりはないですし、宗教観について、絶対性を求めることは大きな間違いですので、深くは語りません。
埋葬は宗教行為であり、宗教行為に絶対の正解はない。
日本人の宗教観
日本人の宗教観というのは、とてつもなく曖昧です。
日本人=無宗教という気はないですが、文化的な催しだけを捕まえても、キリストの生誕祭(クリスマス)をやった7日後には神社に初詣に行くという宗教観は、世界的にも結構レアだと思います。
他方で、ラマダンといった修行的な側面を持つイベントはトコトン取り入れない。
これは信仰対象に軽重をつけているというより、楽しそう面白そうなものだけを取り入れようとする日本人の姿勢と考え方だと思います。
食べ物についても、海外の美味しそうなものは一通り食べてはアレンジしてしまいますからね。ラーメンとか。
先祖は火葬して骨は寺のお墓に祭ってるし、お盆にはお坊さんを呼んで経を挙げてもらったりしていても、自分の流派どころか、自分が仏教徒であるという認識を持つ人は少ないと思います。
実際僕もその一人で、お盆とか一通りイベントはこなしますが、僕自身が仏教徒か?と聞かれるとNOです。
大学も仏教系の大学で、必須科目として仏教を学びましたが、仏教徒ではないです。少なくともその自覚がない。
そんなわけで、日本人にとっての埋葬が宗教的な意識を持つ人はそこまでいないと思います。
周りが火葬なんだから、自分ところも火葬でいいし、当然他も火葬でまとめるよねといった感覚で、日本における埋葬はそこまで宗教的な価値がないと考えている人も多いのではないでしょうか。
僕を指導していただいた憲法学の教授の一言ですが。
「例の大震災に関する合同慰霊祭。アレ政府主催だけど、真っ向から仏教的な弔いだよね?政教分離に反しないの?」
と問題提起されていたのをいまだに覚えています。
その位、埋葬(弔う)という行為について、普遍性を見出すがゆえに特定の宗教観を見出すことが少ない。
日本人にとって、火葬とは宗教行為ではない可能性がある。
また、日本人にとって宗教という単語について、少し忌避観を覚えている方もいるように思います。
日本の歴史を紐解いてみても、キリスト教に対して行われた踏み絵であるとか、おおよそ30年前に行われた新興宗教による社会的混乱であるとか…。
どの宗教がよい悪いという教育ではなくて、宗教が絡むと碌なことがないという一種の刷り込みに近いものが歴史的にあるように思います。
日本人のコミュニケーションテンプレートの一つに「政治と宗教と野球の話はするな」とかいいますから。
要は、対立するような話は最初からするなというテンプレートで、宗教というものがその対立を生む者として認識されている部分でしょう。良くも悪くも事なかれな日本人のらしいテンプレートかもしれませんね。
某政党の支持母体に当たる宗教団体についても、その宗教的教義がなんであるかとか、その政党の政策がどうということではなくて、単に宗教組織であるからという理由で忌避される側面も否定しきれません。
それがよい悪いという話は、それこそ宗教観の正しさのような話になり、多様な宗教観という側面からは逆を行くので、この場では話はしませんが。
日本人は宗教を宗教と認めると忌避する側面がある。
日本人としてこれから考える
これからの時代、考えることは考えないといけません。
客観的な話をすれば、労働人口が減り始めている以上一時的であれ恒久で来てあれ、一旦は外国人の方を日本に招き入れて社会経済活動を支える必要があるため、外の国の人たちのひとくくりでスルーするわけにもいかない時代になりました。
認識をあたらめる必要性を感じているのが、外国人の方にとって宗教についての関心は我々と同じではないということです。彼らは生来の環境故、宗教を持つことが人生における救いになると考えていて、日本人が考える宗教の在り方とは根本的に異なるように思います。
このてん、僕自身が「日本人の宗教とは」と代表者面して断言することではないのでしょう。これまで、僕の経験や環境から推測はしましたが、皆さんそれぞれにとって、宗教というものを一旦整理してみるタイミングといえるかもしれません。その結果として何かを信じなければいけないという話しではないです、ただ、僕たちが日本人としてこれまで生きてきた中に宗教というものがどうゆう関りがあって、それが外国の人とは根本から異なる可能性があると認識するだけで大きく変わると思います。
また、外国人との宗教行為の関係性に考えるうえで、日本の司法判断の先例としてマクリーン事件は理解しておかないといけません。端的に申し上げれば、日本国憲法の保護下にあるのは日本人は当然ですが、権利の性質によっては外国人の方にも同じく適用されます。
宗教活動についてはおそらく外国人の方も補償の範囲に入るでしょう。その後に公共の福祉による制限に服するか、という考えになります。その中で、埋葬が宗教行為として認定された場合、そもそも日本の埋葬法は土葬を禁止はしていないので、特定の地域(例えば街中などの繁華街)での土葬霊園が認められるか?という、場所による制限の可能性はさておき、【土葬を行う外国人は出ていけ】という言説が法的に肯定されることは難しい様に思います。(むしろ、差別発言として別の法的リスクを伴う可能性すらあります)
今回は埋葬についてですが、意外と「我々にとっては何とでもない事」が向こうにとっては重大なことというのはこれからもたくさん出てくるのでしょう。もちろん逆もあるでしょうが。
共生を考える
誤解のない様に申し上げておくと、僕は外国人の方に肩を入れをしたりとか、特定の政治的宗教的思想を推進したいというわけではないということです。
ただ、複雑化してく社会の中で、問題の本質も捉えないまま、ただいがみ合うだけの社会というのは誰しもが望むところではないと思うので、その整理はしておきたいと思ったから記事にしました。
そして、今揉めてニュースになっているのは、専ら「外国人の方の埋葬」の話ではありますが、本来的にはただの「他人との」話のはずなんですね。
例えば、自分の友人が自分の価値観とは異なる宗教観を用いた教義を信仰している場合にどう振る舞うのが適切でしょうか?距離を置く?関係性を整理する?
実のところ、僕にも一人か二人いるんですよね。某大型宗教団体に所属している友人。
でも、じゃあ彼をグループから外すとは考えませんでした、あくまでそれを含めた彼であるはずですし。
なので、グループで遊ぶときに彼が「そっち関係で~」という話しがあれば素直に受け入れました。仕方がないことですし、それが彼の生き方なのですから僕が非難するのもおかしな話です。
無論僕と彼の間で、ちょっとした不文律みたいな感じもあります、例えば勧誘はしないであるとか、教義自体は非難しないが、その出先団体である政治団体の在り方については別であるとか。(ただし相手の言い分は受け入れる)
終わりに~誰しもが隣人~
書きながら僕の中でも整理をかけていたのですが、究極的には「他人の価値観とどう向き合うか」という点に尽きると思います。ただ、その他人が友達なのか、単なる他人なのか、それとも外国人であるか。その違いでしかなくて、その違い故に対応が違うのであれば、それは少し危険かもしれません。
この辺は日本の義務教育からの課題と言えるのかもしれません。周りと違うことがとにかく悪。宿題をしないことが空くなのは、出されたミッションをこなさないから悪なのであって、周りがやってるのにならないから悪ではないはずです。ですが、この周りと違うから悪という風潮が押し出されることがあります。
なぜ違うのか、何が違うのか、違うことの問題はなんなのか。
それを整理しないまま、ただ弾き出すだけだと、やがて生きづらくなっていくのは自分自身かもしれないなと思いました。
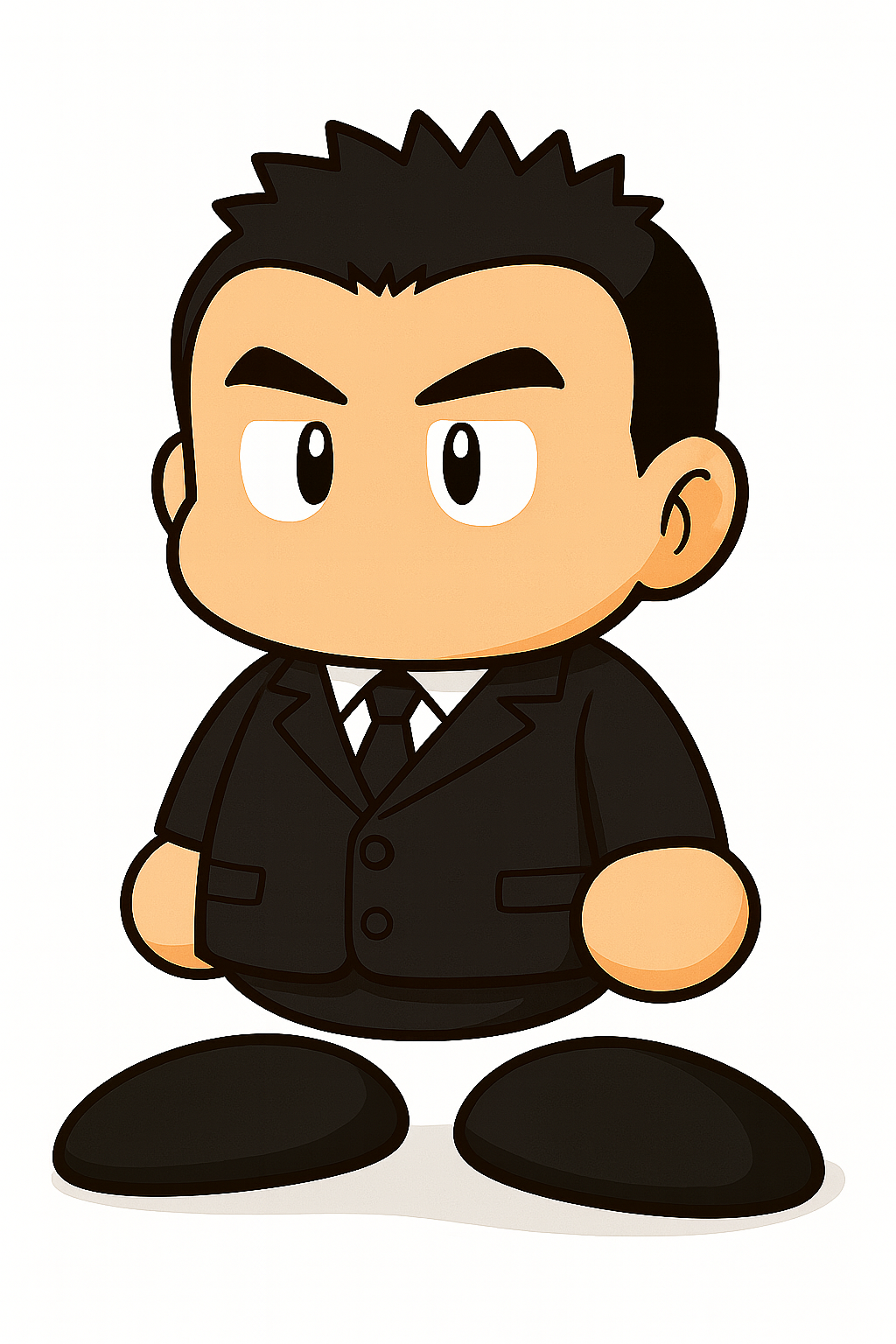


コメント