こんにちは。今回は入管関係の記事の続きです。
前回のような制度の概要説明ではなく、行政書士の現場で「これは常識だよね」とされている注意点をいくつかご紹介します。依頼する側の方にも知っておいていただきたい、大切なポイントです。
これらを知らずに依頼すると、そもそも行政書士が受任できない可能性も高くなりますので、ぜひ参考にしてください。
1. 依頼の関係性 ― 本人・企業との直接面談は必須
行政書士が入管業務で最も注意しているのが、いわゆる「ブローカー」案件です。
具体的には、外国人本人と直接面談できない場合や、雇用先企業と直接話ができない場合は、基本的に依頼をお断りする流れになります。
中には「書類は全部作ったから、これを持って行ってくれ」という依頼がありますが、これは明確に違法であり、行いません。
車の登録業務など「物」に関わる分野では、書類だけを持参するケースが一部存在します。しかし「人」が入国・在留する案件では、国としてより慎重な判断が求められます。
私の場合も、依頼を受ける際は必ず外国人本人と一度は面会し、(既に保有しているなら)在留カードを確認することを条件にしています。ここをクリアして初めて、手続きの話が進んでいきます。
2. 入管業務は「絶対通る」とは言えない
多くの許認可業務は、必要な書類や条件が揃えば認められる方向に動きます。不許可になるのは、書類の不備や欠格事由(過去の刑罰歴など)がある場合がほとんどです。
ところが入管業務は逆で、許可が下りるかどうかの見込みを立てるのが非常に難しい分野です。国の裁量が非常に強く、場合によっては同じ条件でも結果が変わります。
例えば、同じような内容で申請しても、一方は3年の許可が出て、もう一方は1年しか出ないことがあります。さらには、一方が許可されても別の人は不許可になることも珍しくありません。
このため、私は依頼を受けても「絶対に通ります」とは決して言いません。
3. 入管法のスタンス ― 日本人の雇用が優先
入管法は外国人を受け入れるためのルールですが、実際には「安易には入れたくない」という考え方で作られていると感じます。
例えば、民泊や経営・管理ビザ(個人事業主が自らの権利で入国するケース)は別枠として、技術・人文知識・国際業務ビザや一般的な就労ビザについては、まずは日本人で賄うというのが原則です。
この言い方は政治的な「日本人ファースト」に近い響きがありますが、入管法の根底にあるのは日本人の雇用調整です。日本人が職にあふれている状況で、外国人を入れて仕事を与えるという発想は認められていません。
ただし近年、日本人労働者が余っていても希望者が集まらない職種が増えており、その「空席」を埋めるために入管制度が一部動いている現状があります。
4. 入管法は改正が多く、動きが軽い理由
入管法は改正が多く、非常に動く法律です。
この記事を書いている時期にも、経営管理の在留資格と民泊の特区制度のかみ合わせが悪く、意図しない外国人が入国している現状を鑑みて、改正の動きが聞こえています。
その理由の一つが、守っているのは主に日本人の権利で、制限しているのは外国人の権利だからです。
日本の法律は、まず日本人を守ることを最優先とし、そのうえで外国人にも必要な権利を認めます(マクリーン事件参照)。
そのため、外国人の入国や在留に伴う行動が日本人の権利を脅かすと判断されれば、国は迅速に動きます。これは差別やナショナリズムではなく、多くの国に共通する考え方です。
例えば、日本人労働者が大量にある国に入り込み、現地の人が働けなくなれば、どの国でも反発や混乱が起こります。入管法も、こうした「自国民の経済を自国民で守る」という前提に基づいて運用されているのです。
まとめ
入管業務は、他の許認可業務とは異なる独特のルールと判断基準があります。
- 本人・企業との直接面談は必須
- 許可の可否は予測が難しい
- 日本人雇用が優先されるスタンス
- 改正が多く、国の裁量が強い
依頼をする側も、これらの背景を理解して臨むことが、スムーズな手続きへの第一歩となります。
この形であれば、そのままブログに掲載でき、SEO的にも「入管法」「行政書士」「許可の可否」「日本人雇用」などのキーワードが自然に入っています。
もしご希望であれば、この記事の冒頭に導入文とアイキャッチ画像用キャプションも追加できます。
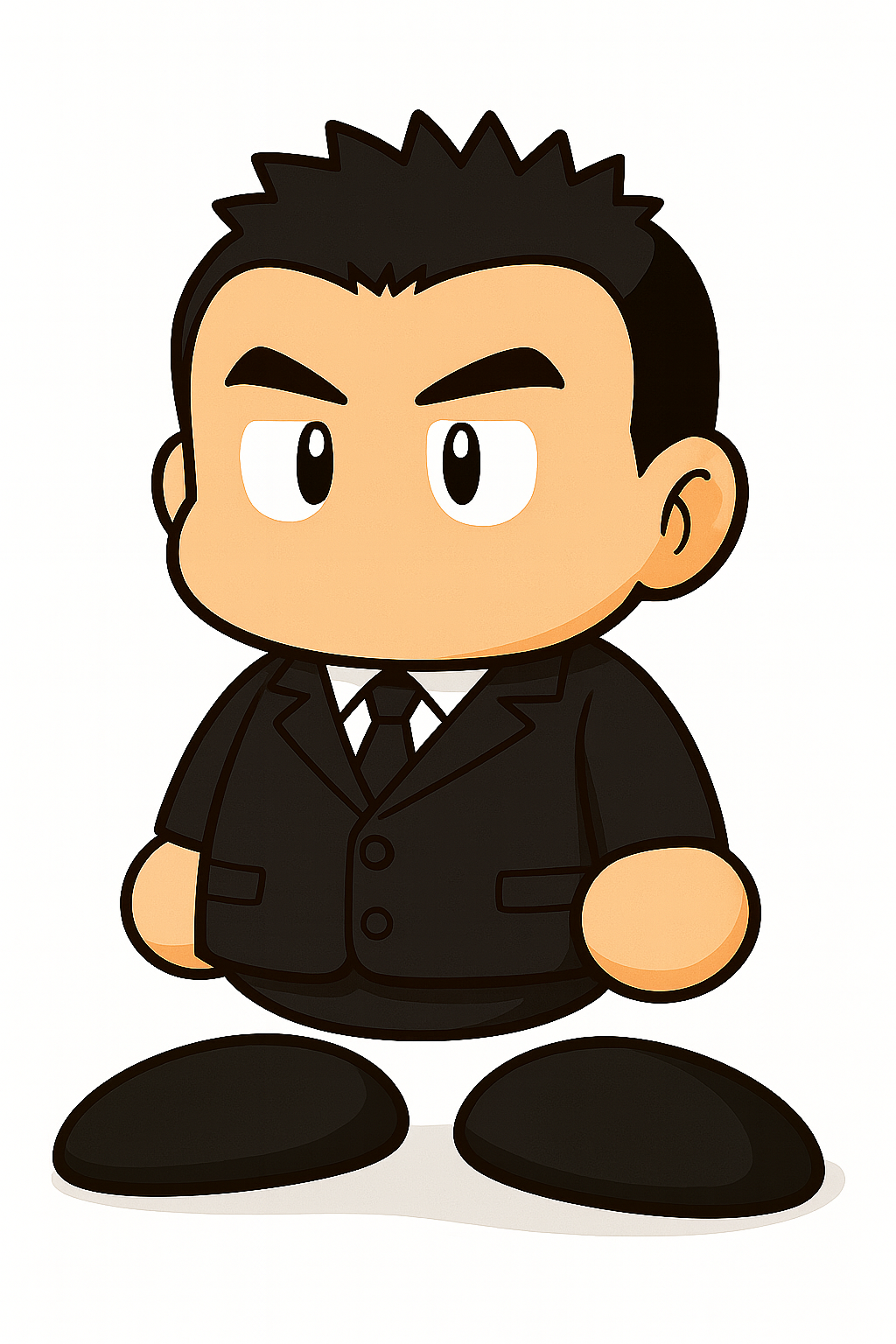



コメント